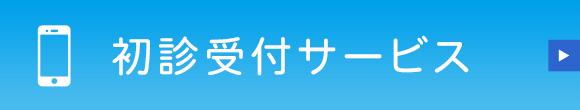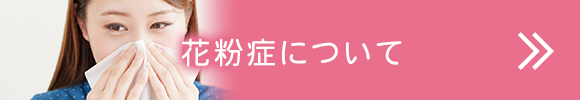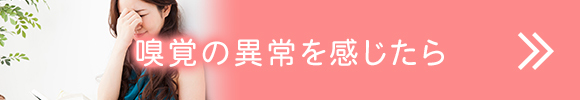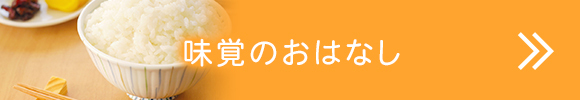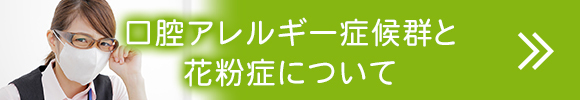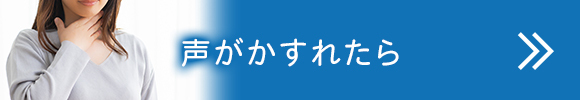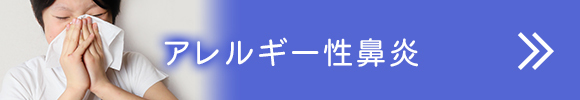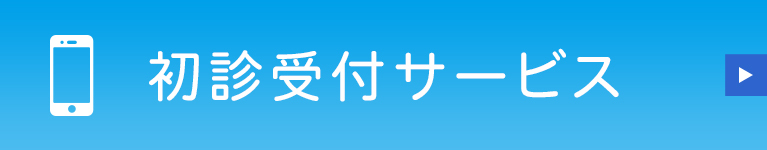松本市岡田下岡田仲田
四賀線「松岡東区」バス停
耳鼻咽喉科・気管食道科
開院後20年以上経ち日々地域医療に邁進しています。
当院は院内でお薬をお渡ししています。
ワクチン接種の方は直接お電話で医院にご連絡を下さい。
当院からのおしらせ
●2024/04/19 診療時間変更のお知らせ 4月27日(土)より土曜日の診療時間が8:45~12:30に変更となります。
●2022/09/15 ホームページをリニューアルいたしました。今後ともよろしくお願いいたします。
診療のご案内
お役立ち情報を掲載しています
診療時間
医療法人横田耳鼻咽喉科医院のご案内
■院長
横田 耕二
■所在地
〒390-0313
長野県松本市岡田下岡田仲田220-1
■診療科目
耳鼻咽喉科・気管食道科
■電話番号
0263-46-8881